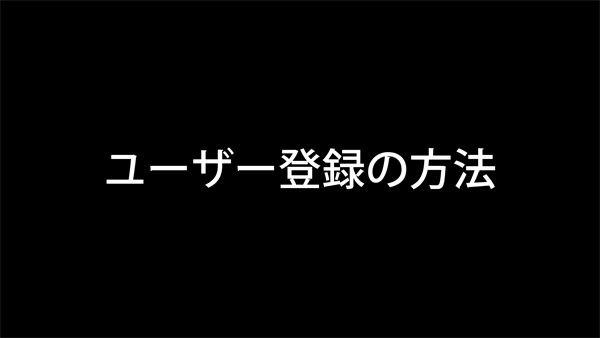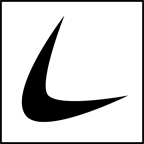津軽氏城跡 堀越城跡
津軽氏は、系図では光信を始祖とし藤原秀郷を遠祖としています。しかし、諸史料からみると、南部氏の一族であったようです。はじめ種里(西津軽郡鯵ヶ沢町内)に住し、のち大浦(弘前市内)に移り大浦氏を名乗りました。そして、光信から五代後の為信が大浦城を本拠として津軽から南部氏の勢力を一掃し近世大名として津軽氏と称するようになったものです。元亀2年(1571年)、その口火を切る南部氏郡代の居城石川城攻略の前線基地となったのが、堀越城です。堀越城の歴史は、南北朝時代の建武3年(1336年)北朝方の武将曽我貞光が堀越に楯を築いたことに始まります。草創時の規模やその後の変遷は不明ですが、為信の実父という武田甚三郎守信の居城となり、更に為信が領知することになったといわれています。天正18年(1590年)、豊臣秀吉に拝謁して津軽の領有を認められた為信は、文禄3年(1594年)本拠を大浦城から堀越城に移し、あわせて家中諸士、神社仏閣、商家なども堀越へ移住させました。これは、政治及び経済面での領内支配強化のためといわれています。しかし、家臣の反乱で本丸が陥落するなど、軍事面からみると堅固な城ではなかったようです。このため為信は新城の建設を計画し、二代藩主信枚が慶長16年(1611年)高岡(弘前)に居城を移し、津軽氏の本城としての堀越城の役割は終わりました。堀越城は平城である。その規模を示す当時の史料はほとんどありません。しかし現在でも本丸の土居や堀跡はよく残り、当地方の城郭の変遷を知る貴重な遺構であるとともに、津軽氏の発展過程を示すものとして重要です。

広告
| コンテンツ ID | C-170206-095750-941151 |
| カテゴリー | お出かけ情報ナビ > おすすめスポット |
| タグ | 弘前市, 見る, 文化史跡, 城郭 |
| 場所 | 青森県 弘前市大字堀越 |
| 出典 |
このコンテンツは,以下の著作物を改変して利用しています。 公共クラウド (総務省),観光情報,公共クラウド利用規約 |
| ライセンス |
CC ライセンス 表示 2.1 日本

|
| 閲覧数 | 259 |
| ウォッチ数 | 0 |
| 更新日時 | 2017/02/06 11:34:57 |
※ マップ上のマーカーは,関係のある地域の代表的な地点,またはおおよその位置のみを示している場合があります。
広告
ウォッチリストに追加しました。